 
第4話(その2)
「クレティナス軍、突入してきます」
千年帝国軍第七艦隊旗艦ビルスクニールの艦橋に、情報士官の声が響いた。
コンピューターによって画像処理が施されたクレティナス艦隊の勇姿が、圧倒的な量感を伴ってメインスクリーンに映し出される。
「一転して、今度は速攻か。なかなかやるな」
至近距離で発射されたビームとビームが衝突して粒子が弾けとぶ。ミサイルの直撃をくらった戦艦が瞬時に火球と化す。宇宙母艦から出撃した戦闘機が、艦を防衛するアースムーバーと宇宙を舞台に激しい戦闘を繰り広げる。戦場は人命と物資とエネルギーの大量消費を続けた。
急襲したクレティナス軍の一撃で、帝国艦隊の艦列に乱れが生じた。最前列の陣が破られ、エネルギーの閃光と破壊の衝撃が旗艦ビルスクニールを襲ったのである。アルフリートの速さと攻撃力はタイラーの想像を越えていた。指揮の統一性といい、一糸乱れぬ艦隊運動といい、彼の対戦したどんな敵よりも上であった。
だが、タイラーも負けてはいない。常に戦局を冷静に見つめ、正しい判断を降してきた彼は、指揮官席に落ちつきはらって座り、部下に指示を与えた。
「後退しろ。後退しつつ陣形を再編、体勢を立てなおす」
アルフリート・クラインの苛烈で強力な攻撃は、一点に集中し帝国軍の陣を削る。対するタイラーは、艦隊を後退させながら陣を再編し、比較的大きい凹陣形を敷いて長距離からの半包囲戦に持ち込んだ。
両軍は、しばらくの戦闘の後、互いの距離を置いて再び膠着状態に入った。
戦場における純粋な戦闘能力は、三つのベクトルによって現すことができる。攻撃力、防御力、速度の三点である。神将タイラーはこれらの点で、常人の域をこえた才能を、高い次元でバランスよく保っていた。それに対して、「赤の飛龍」と呼ばれるアルフリートは、攻撃力と速度でタイラーを凌駕し、防御でも並々ならぬものがあった。
「それにしても、すごい奴だ。私が一瞬も気を抜くことができないとはな」
やや、自嘲ぎみにタイラーは呟いた。クレティナス軍の一時的な急襲は防ぎ切ったものの、一瞬でも艦列を乱され、旗艦近くまで侵入されたことは、彼にとって恥ずべきことだったのだ。
「さすがに『赤の飛龍』と呼ばれるだけのことはあります」
「赤の飛龍か。戦場を翔めぐる赤き飛龍、よく言ったものだ。攻撃といい、スピードといい、すばらしいとしか言いようがない」
アイスマンの言葉に同調するようにタイラーはうなずいた。
「だが、彼らも人間だ。あれだけの動きを長時間続けては、将兵の身が持たないだろう。チャンスはこちらにもある。持久戦に持ち込むことさえできれば、私に敗北はない」
「ですが、時間を与えては、敵の別働隊が何をするかわかりません」
「そのとおりだ。今の私がやらなくてはならないのは、短時間で彼らを破ることだ。こんなところで、時間をつぶしている暇はない。……そう、暇はないのだ」
戦況を見つめるタイラーは、最後は自分に言い聞かすように言った。
後に「バルディアス会戦」と名付けられたこの戦いは、銀河辺境部の強国クレティナスと銀河中央部の支配者、千年帝国との本格的な戦争の始まりを意味していたと同時に、後の時代を築いた二人の若き英雄アルフリート・クラインとユークリッド・タイラーの最初の出会いでもあった。
速戦即決を得意とする「赤の飛龍」と持久戦を得意とする「神将」の対決は、当然、興味深いものだったが、バルディアス会戦における両者の戦闘は、互いに満足のできるものではなかった。クレティナス軍は、分離した別働隊を待つために時間を稼ぐ必要があったし、帝国軍は、敵の別働隊に備えるために短時間でクレティナス軍を破らねばならなかったのである。
ただし、クレティナス軍はベルソリック、ブラゼッティ、グエンカラーの別働隊が到着し、小惑星を「バルディアスの門」に衝突させるだけで目的を達成することができたのに対し、帝国軍は正面に現れた敵を現有戦力で撃退していくことしかできなかった。要塞を防衛し、外敵の帝国領への侵入を阻止するを任とするタイラーの戦闘は、常に受け身であった。
「時間の勝負だ。クレティナス軍の待つものが早いか、我々が彼らを倒すのが早いか。数的にはこちらの方が敵の二倍はあり、まず有利と言えるだろう。だが、もう時間が残っていないかも知れない」
物事を悲観的に考えては、あらゆる事象に対して積極的な行動をとることができない。しかし、エンリーク・ソロの思考は、どうしてもよからぬ方向に向った。ヴァルソ・カルソリーという決して有能とは言えないかつての上官と違って、現在の彼の上官は「神将」とも呼ばれる名将であった。それなのに、彼の思考は変わらなかった。
「敵がアルフリート・クラインだからなのか?」
両方に共通した部分をあげるとそれしかない。
「もしそうだと言うのなら、何故、俺は彼に勝てる気がしないのだろうか?」
エンリークは自問したが、望ましい結論の出る問題ではなかった。
戦局は膠着している。タイラーの第七艦隊とアルフリートの第四九艦隊は20光秒の距離をおいて対峙したまま動こうとしない。帝国軍はすでにオーエン・ラルツ中将の第一九艦隊を分離して、クレティナス軍の背後をうかがわせようとしていたが、まだ成功はしていない。ただ、貴重な時間だけが無意味に費やされている。
開戦からすでに二時間が過ぎようとしていた。両軍の損害は互いに軽微ではあったが、若干、帝国艦隊の損耗率の方が高かった。アルフリートの強烈な一撃が影響していたのは言うまでもないが、戦況全般において、クレティナス軍が戦いの主導権を握っていることが大きかった。
バルディアス会戦が第一段階に終わりを告げ、第二段階に突入したのは、標準時間一七時三○分、開戦二時間三○分後のことだった。 最初の変化は、帝国軍の別働隊、第一九艦隊によってもたらされた。戦場を離れ、クレティナス艦隊から見て右方向を迂回した艦隊は、アルフリートが背後を防御するために散布した誘導機械宙雷の網を突破して、クレティナス軍の後方に回ることに成功したのである。
「撃て、撃て!」
老将ラルツの叫びとともに、帝国一九艦隊六五○隻が一斉にうなりをあげ、光の龍がクレティナス軍に襲いかかった。クレティナス艦隊の大半は注意が前方に向けられ、後方の防御は数十隻の艦艇と数万個の誘導機械宙雷に依存していた。しかし、アルフリートの八倍の実戦経験を持つラルツ中将は、長年の経験を生かして機雷群をかわし、ポイントを絞って突破してきたのだった。
クレティナス艦隊は完全に帝国軍の挟撃体制にはめられた。前面に神将タイラー率いる第七艦隊、背面に老将ラルツ率いる第一九艦隊、どちらも、難敵であった。
「機雷群を突破したというのか、こんな短時間のうちに」
アルフリートは情報士官の報告を疑った。指揮官席から立ち上がり、コンソールに表示される戦況報告に視線を投じる。
艦隊の後列が帝国軍の攻撃で混乱し浮き足立っていた。前方では、タイラーと互角の勝負を繰り返しながら、後方から徐々に陣を崩されていく。
「なんという醜態だ。これでは、敵のいい射撃練習台じゃないか。後方は何をやっているんだ。陣形を正して応戦しないか」
アルフリートの表情が険しくなった。彼にしてはめずらしいことである。
帝国艦隊のビームが漆黒の空間を無音のまま切り裂き、クレティナス軍の戦艦の推進装置に直撃する。動力炉の爆発とそれに伴う誘爆が艦全体の爆発につながる。艦隊後列は爆発光とエネルギー乱流の渦に包まれた。
「二倍の敵に囲まれては、勝利はおぼつかないか。くそ!あと、一時間、一時間だけもてばいいんだ……」
アルフリートは右こぶしを握り締め、それをコンソールに叩きつけた。若さゆえの甘さなのだろうか、アルフリートは表情を蒼白にし体を震わした。彼は、一瞬、死を予感していた。
「閣下、まだ負けたわけではありません。『赤の飛龍』とも呼ばれた方が、このようなことで取り乱してどうするのですか。あなたは、二○万にも及ぶ将兵の生命を預かっているのですよ」
声がしたほうに振り向いたアルフリートの前に、彼より二つ年長のファン・ラープ准将が立っていた。不真面目が当然な姿になっているラッキー・ファンが、真剣な顔をしてアルフリートのエメラルドグリーンの瞳をのぞいていた。
「ファン……」
「逃げたっていいではないですか。死ぬことに比べたら数億倍もましなことです。生きていればできることが沢山あるのですから。それに、まだベルソリック提督の戦力が残っていますし……」
「すまない。司令官の私が取り乱してしまって」
アルフリートは片手をあげて、ファンを制した。
大きく深呼吸をし、一度、艦橋を見渡す。そこには、司令官の指示を待つ将兵たちが、不安な目を向けていた。「みんな、すまない」心の中で呟いてアルフリートは意を決した。
「撤退する。艦列を整え、天頂方向に向けて……」
しかし、すべてを言う前に、情報士官の叫び声が割り込んだ。
「帝国軍の後方に未確認艦隊。識別信号ブルー。味方です。味方の艦隊です!」
「おれたちは助かったんだ」
「飛龍」の艦橋が一瞬、歓喜の声に包まれた。
それは、朗報であった。
ラルツ中将率いる千年帝国艦隊の背後に、新手のクレティナス艦隊が出現したのだ。ベルソリックでも、ブラゼッティでも、グエンカラーでもない、第四九艦隊以外のまったく別の艦隊であった。艦数五○○隻。それは、かつてアルフリートが指揮していたクレティナス最強の艦隊、第四四艦隊であった。
アルフリートはまったく予期していなかった。帝国軍も不覚にも備えていなかった。グランビル少将率いる第四四艦隊の到来は、バルディアス会戦の戦局を変える第三段階の始まりを意味していた。
戦況は一変した。
背後からの攻撃に、追う立場から追われる立場になったラルツ中将の帝国軍第一九艦隊は、陣形を再編しつつ戦場を離脱し、第四四艦隊の追撃を振り切ってタイラーの本隊に合流した。
一方、アルフリートの第四九艦隊は、なんとか体勢を整えて、第四四艦隊に合流することに成功した。
「アルフリート、無事でなによりだった」
通信パネルが開かれて、そこに映し出されたのは、アルフリートの旧知の顔だった。グラン・フォール・エル・グランビル少将。長い名前のために、めったに全部を言われることはない。通常、彼は姓のグランビルで呼ばれている。
「グランビル!」
アルフリートの口にした名前には、彼のあらわしきれない気持ちが込められていた。敗北寸前の窮地から、再び勝利の可能性を信じて戦える身になったのである。士官学校時代の友人に対して、心から感謝した。
「ベルトール元帥の命令で来てみたが、よかったよ。しかし、おまえには驚かされる。神将タイラーを相手に、半数の戦力で戦いを挑むとはな。無茶なことをしたものだ。何か勝算でもあったのか」
「なに、賭けが好きなだけだよ。結果はやってみなくては、わからんからな」
「戦略家の言葉とはとても思えないな」
アルフリートとグランビルは不謹慎にも笑った。戦闘中にもかかわらず、ほっとした和やかな雰囲気がそこにはあった。
「そんなことより、指揮を頼むぞ、総司令官閣下。吾が四四艦隊もクライン中将とともにタイラーと戦うんだからな」
「ああ。しっかり使ってやるよ」
クレティナス軍は戦場から三○光秒(約一五分の距離)後退して、体勢を整えた。先程の戦闘で第四九艦隊七○○隻中およそ一三○隻が破壊、あるいは戦闘不能の状態されていた。アルフリートはこれらの艦艇を後方に下げ、四四艦隊の五○○隻と戦闘可能な艦艇五七○隻を集めて布陣しなおした。
対する千年帝国軍は、タイラーの指揮のもと、バルディアスを一八○光秒の後方にして平陣を敷いた。クレティナス軍との相対距離は九○光秒と開くことになった。
|
 |
  |
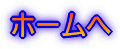
|

